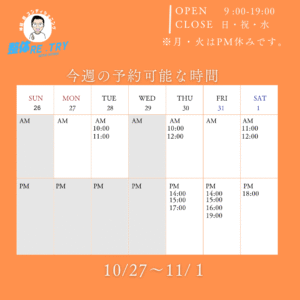痛みとは何なのか?
今日はそんなお話。
施術を行なっていると同じ部位、同じ疾患名なのに痛みの出る部位や、強さ、動作は各々異なります。
なぜこのような場合があるのか?
まず、痛みの種類というか、発生要因は大きく分けて3つに分けられます。
1:侵害受容性疼痛
2:神経障害性疼痛
3:痛覚変調性疼痛
字面だけ見ると何のこっちゃ分からんとなると思います。
ものすごく簡単にすると。。
1:ケガなどで腫れたり、血が出たり、熱を持ったりすると出る痛み。
2:神経の繊維の働き(動き)が悪くなっていると出る痛み。
3:受診をしても明確な原因がなく痛む。社会的な要因が大きく関与する痛み。
こんな感じになります。
ケガが要因の場合。
特徴として、ピンポイントに痛みが出現し、腫れたり、出血したり、赤くなったりと、見た目にも分かるほどの変化が見られます。
炎症症状が強く出るので、徒手での施術は炎症を促通してしまう可能性があります。
適切な医療機関に受診し、骨折や内部出血の有無の確認を行うことが最優先となるので、しっかり検査を受けてください。
その後、経過に合わせた徒手のアプローチが可能です。
神経繊維由来の痛みの場合。
安静にしていても痛みが出やすく、見た目には分かりにくいことが多いです。
徒手で行う神経の伸長検査や絞扼テストを行うと決まった症状が出るのが特徴です。
代表的なものだと坐骨神経痛が聞き慣れていると思います。
慢性化しやすく、症状の出る部分以外が要因の場合も多いです。
神経の走行上のどこに絞扼や滑走不全が起きているのかを特定する必要がある痛みです。
脳と脊髄は中枢神経、そこから伸びる神経が末梢神経と言います。
徒手でアプローチできるのはこの末梢神経になります。
社会的な要因が関与する痛みの場合。
鑑別がとても難しいです。
ストレスといえば簡単になってしまいます。
ストレスという大まかな括りの中に各個人のプライベートの問題が多く、徒手での対策は難しい側面があります。
ここまで「痛み」に関してお伝えしましたが、実際は、これらの痛みを併発している場合が多く見られます。
例えば、ケガは完治したのにまだ痛みが残る場合は、
ケガが要因で周辺組織(神経、血管等)の滑走不全や、疼痛の長期間の持続に伴う活動制限があったことに対する心理的、身体的なストレスも関与していると自分は考えます。
それらは同時に起こるのではなく、時間経過や、受傷部位、日常生活などの多岐にわたる要因で起きる問題だと自分は思います。
色々な要因で痛むことを理解することで改善する方法も同時に見つかりやすくなります。
自分の痛みは自分しかわからない。
確かにその通りです。
どれだけ辛いか、どれだけしんどいかは他者には伝わりにくいです。
しかし、何が原因ですか?心当たりはありますか?と質問すると、
急に痛くなった。ケガしたからなど、意外と具体的に見つけ難いことが多いと思います。
自分でも気づき難い要因を明らかにし、アプローチ、セルフケアを行うことで改善を早めることができると私は考えます。
この痛みは何が原因なの?
どうしていつまでも変化がないの?
そんなお悩みの方、ぜひ一度当院へ来ていただけると幸いです。
人生の一助になれるようにできうる限りの方法で改善を目指します。